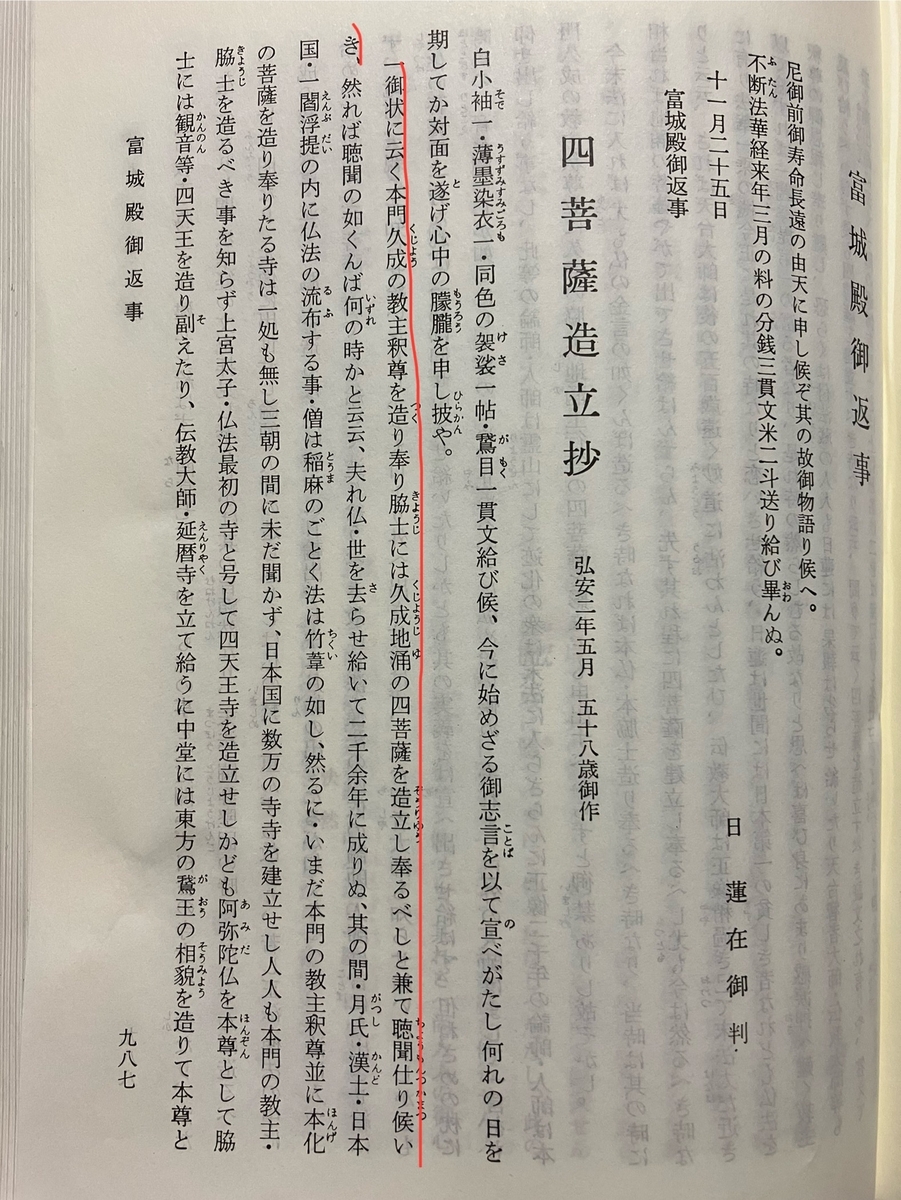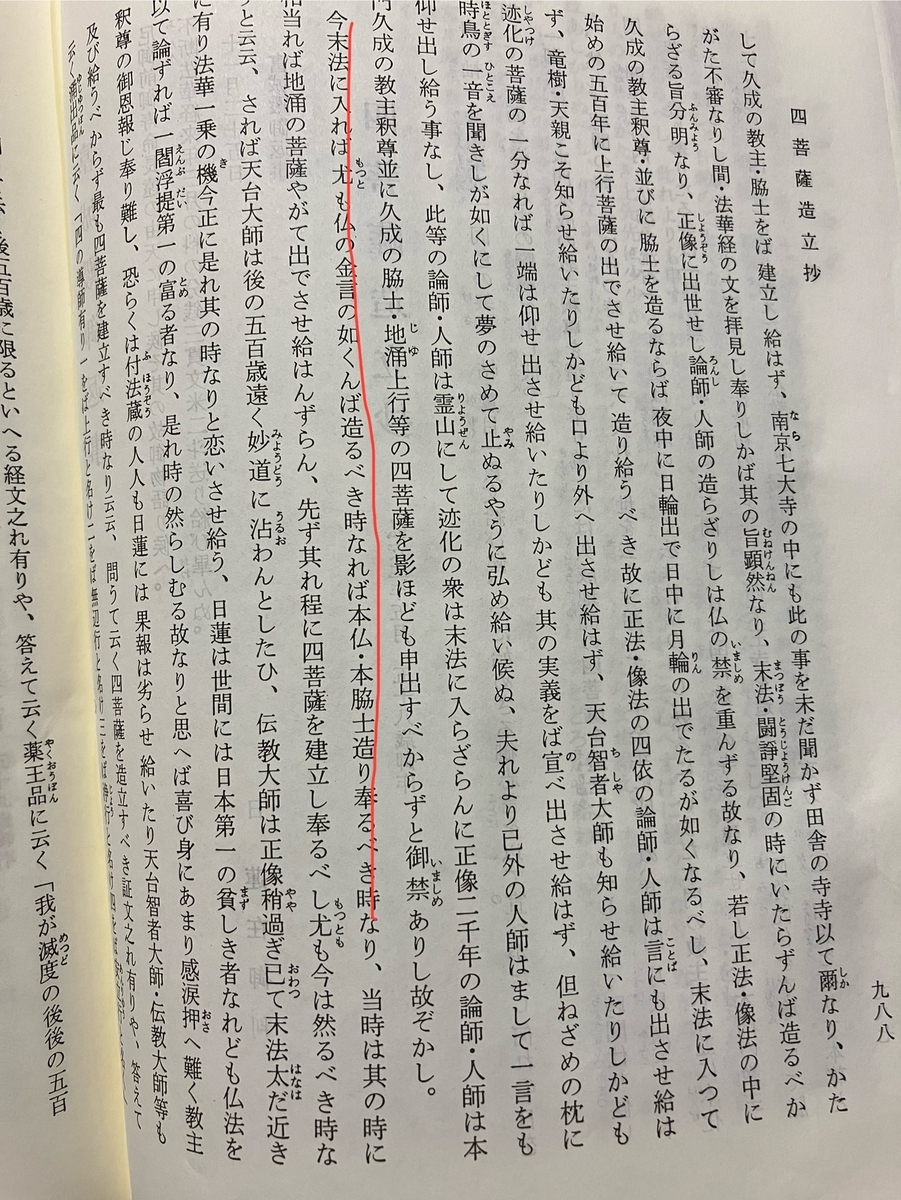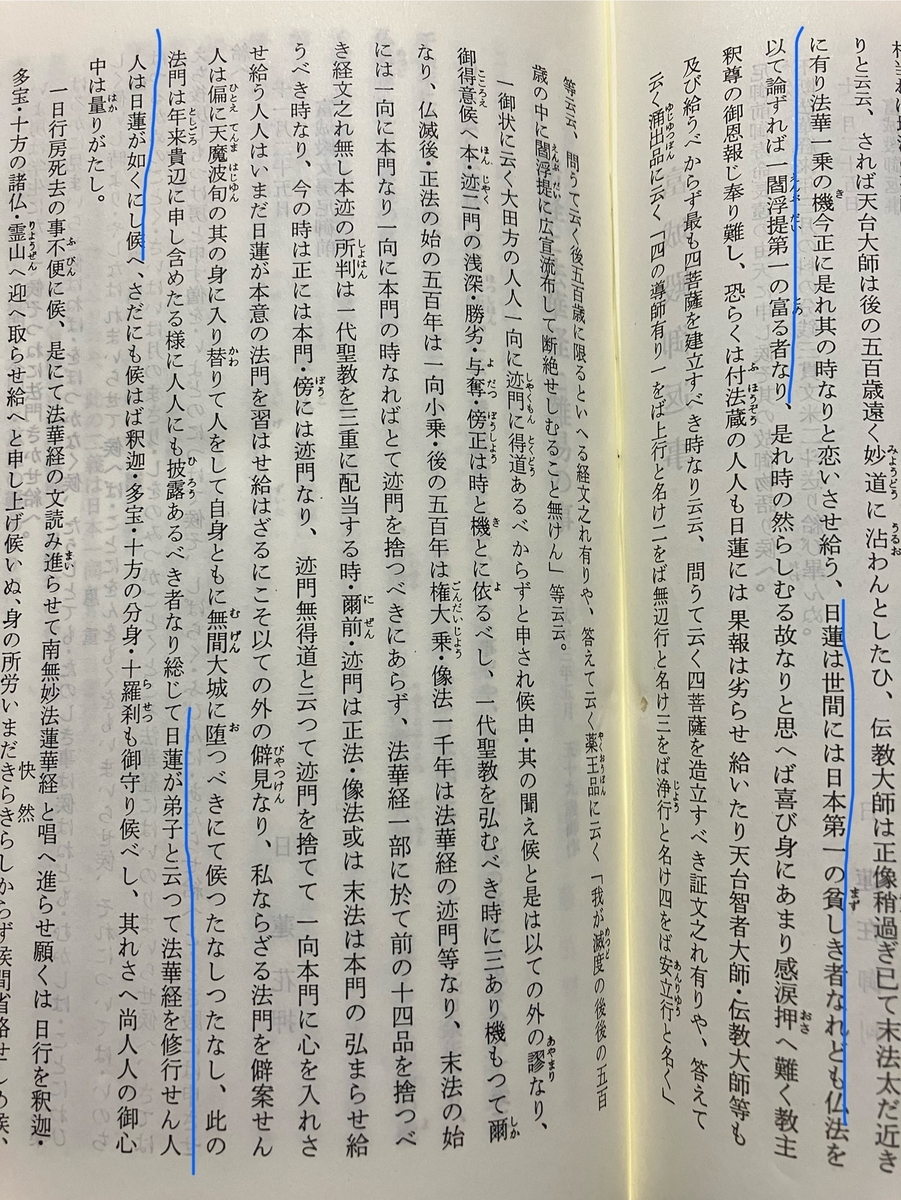いつもみなさん、ありがとうございます。
こんなブログを書いていまして、私が小難しい教学の記事を書くことも多く、「気楽非活さんは教学の知識がある」と言われることもあるのですが、本人は全然そんなことを思っていません。
というのも、私は単なる広宣部上がりの元活動家というだけ。しかも研究者のような方から見れば日蓮真蹟の翻刻もできませんし、そもそも各寺所蔵の真蹟等を実地調査した訳でもありません。鎌倉時代の文献が読める訳でもありませんし、僧籍にあるのでもありません。サンスクリット語も読めませんし、漢訳教典や大蔵経等を網羅して読んだ訳でもありません。
こんなブログを書くにあたり、各記事に参考文献で挙げている研究者たちの論文を読むこともありますが、優れた人たちの研究を読むにつけ、自身の研鑽の不足、また能力の無さを実感します。
私がこのブログで書いていることは、私がそれらの研究等を読み、文献を一つ一つ可能な範囲で収集し、理解できる範囲で日蓮遺文や経典類を読み、わかったことを少しずつまとめてきたものなのです。
その原点はどこにあるのかと言われれば、元活動家、元広宣部だったことがやはり大きいのでしょう。
社会人になって数年目、ちょうど創価学会の男子部メンバーの活動家として動き出した矢先ののことですが、広宣部に誘われました。
「広宣部」とは創価学会男子部の人材グループである「創価班」(創価学会の会館駐車場の警備や整理役員、会場内警備を担当する男子部グループ)の中の一組織という位置付けで、本来は顕正会対策の一環として一部組織に行われていたものが全国展開していくことになります。私が入ったのはそんな時期と重なり、また創価班だけでなく「牙城会」(会館警備、電話対応、施錠等を担当する男子部グループ)でも同様に「言論企画部」(方面や地域によっては「言論企画局」とも言いました)も立ち上げられた時期でもありました。
そんな広宣部・言論企画部でまず学習したのは顕正会対策です。当時の(1990〜2000年代だったように記憶しますが)創価学会組織では顕正会の活動家による活発な家庭訪問が頻発し、その対応に追われていたのです。
顕正会の次は妙観講対策でした。彼らがどんな教義を信じているのか、創価学会とどこが違うのか、彼らが元々言っていたことは何なのか、史料等から明確にし、相手を回答不能に追い込むことこそ広宣部の主たる任務でした。
もちろんそれ以外にも日蓮正宗寺院の張り込み、本山への隠れ登山、末寺への潜入と末寺住職の御講発言の隠し録音、末寺の御講に来る日蓮正宗信徒の人数の把握と隠しビデオ撮影、信者の車のナンバーの記録……今では語るのも憚られるようなストーカー行為に近いことが普通に行われていました。
一時期、広宣部メンバーを増やしていた時期もありましたが、それらは御書や文献を丹念に読む「対論グループ」とは別にストーカーまがいに近いことを行う「実働隊グループ」になることが多かったように思います。実際、御書を使った対論はディベートの技術も必要で、苦手意識を持つメンバーも少なくありませんでした。
そういう対論が苦手な実働隊メンバーたちは、いざ対論になると「囲み折伏」のように多勢で相手を囲んで追い込むタイプが散見されました。次第に何年か経つうちに、私のように対論だけで他者と一対一の議論をする広宣部メンバーは少数派になります。やがて広宣部はほとんどの地方組織で廃止されることになります。
ところで、私のような「対論グループ」に近い元広宣部メンバーたちには、活動が沙汰止みになっても文献や史料の収集や読解を怠らず行っていた人たちがいました。私も区圏や県組織に独自資料を作って提供していたこともあり、しばらくは個人の研鑽を続けていたのです。
とても不思議なことは、2016年以降、私がこのブログを書くようになって数年後くらいに、各方面に点在する元広宣部の「対論派」の人たちから多く情報提供を頂くようになったことです。対論を重視する中心的なメンバーには波田地克利氏の流れをくむ「自活グループ」に近い人たちもいたのですが、それとは別に完全に創価学会教義から離れて研鑽を続ける一部の広宣部メンバーも存在していたことになります。
彼らの情報提供から書いたブログ記事は一つや二つではありません。また情報提供者も一人や二人ではありません。全国に散らばっている元広宣部たちの一部の既に組織活動から離れている人たちが私のブログを読んでくださり、教団や池田大作氏、また広宣部の活動や自活グループらの偽善に気づき、私に連絡を下さるようになったのです。私はてっきり一人で孤立する存在かと思っていたものが、自身が独りではないことを再確認するようになります。
私は2016年からこのブログを書いていますが、正直こんなに長く続くとは思ってはいませんでした。私はほとんど孤立状態で話せる仲間も家族も失われていました。ところが、全国に散らばる退会者や非活・未活メンバー、大石寺の棄教・離檀者たちが私のブログを読んで、反応を寄せるようになったのです。その中には何人かの元広宣部メンバーもいました。
彼らは多くがさまざまな史料を所蔵しており、また現在もなお史料収集や関係者への取材を続けている方もいまして、私にさまざまな形で情報提供をしてくださるようになりました。ブログ記事にはそのことを注記で書いている記事もありますし、また当事者の都合で詳しく情報提供者のことを書けない記事も存在します。しかしながら私はそれらの退会者や元広宣部メンバーたちから執筆の協力を受けることができるようになりました。
彼らの史料提供は教団内部事情の暴露から、教学的な史料の提供まで幅広くメール等で送付して頂いています。当事者の方の解釈をやや客観的に書くきらいも私のブログにはありますが(それがこのブログの特徴でもあるのですが)、概ね私の執筆を好意的に受け取ってくださっています。改めて感謝申し上げます。
みなさまに支えられて今日もブログを続けていけることに本当に感謝しています。どこまで続けられるのかわかりませんが、みなさまの力を得ながら自分らしく「気楽に」書いていこうと思います。いつもみなさん、ありがとうございます。