いつもみなさん、ありがとうございます。
さて昭和40年7月25日、日大講堂で開かれた創価学会第63回本部幹部会にて、池田大作会長(当時)は以下のような指導を行います。私は非常な違和感を感じるのですが、果たして読者の皆さんはどのように感じられるでしょうか。ここでは将来的に起こる「広宣流布」について、その際に何が行われるのかを語っています。
「どんなに公明党が発展しようが、広宣流布は御仏智であります。そしてまた猊下のご一念であられるのです。広宣流布の時には、不開門(あかずのもん)が開きます。その時は、どういう儀式になるか。それは私ども凡下には測り知ることはできません。広宣流布の時は、国が最高に繁栄している時であり、一国のためにも、国民のためにも未曾有の幸福の時です。そうした背景のもとに広宣流布の儀式が行なわれるのです。それが創価学会の究極の目的の一つです。
その時には不開門が開きます。それを開くのは、一義には、天皇という意味もありますが、再往は時の最高の権力者であるとされています。すなわち、公明党がどんなに発展しようが、創価学会がどんなに発展しようが、時の法華講の総講頭であり、創価学会の会長がその先頭になることだけは仏法の方程式としていっておきます。
後々のためにいっておかないと、狂いを生ずるから言うのです。私は謙虚な人間です。礼儀正しい人間です。同志を、先輩をたてきっていける人間です。だが、そのため、皆さん方がかえってわからなくなってしまうことを心配するのです。そうなれば、こんどは皆さん方が不幸です。学会も不幸です。本山にも不祥事を起こしてしまう。その意味において、きょうは、いいたくないことでありますが、将来のために、私はいっておきます。
私が不開門(あかずのもん)を開いて、このように広宣流布いたしましたと猊下をお通し申して、大聖人様に、一閻浮提総与の大御本尊様にご報告することが、究極の、広宣流布の暁の、その意義なのであります。それまでがんばりましょう。


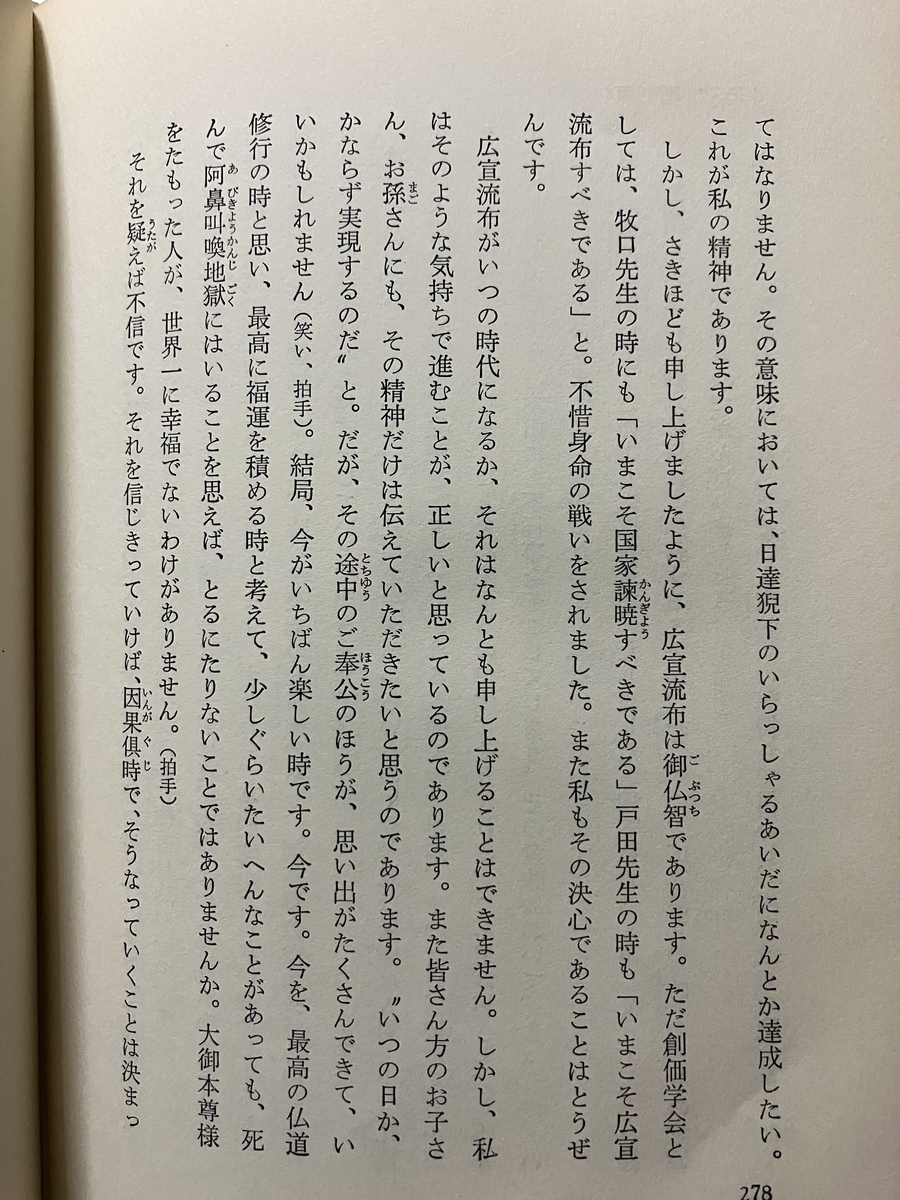
ここで書かれる「不開門」(あかずのもん)とは、日蓮正宗の総本山大石寺の客殿(当時は創価学会建立寄進の「大客殿」)の正面にある小さな門のことで、別名「勅使門」(ちょくしもん)とも呼ばれます。この門はその名の通り、常に閉ざされており、「広宣流布」の時に至って初めて「不開門」が開かれるとされています。
ここで昭和40年当時の池田大作氏が述べているのは、要約すると次のようなことになるかと思います。
①広宣流布は御仏智である。
②広宣流布の時には「不開門」が開く。
④このことは後世のために言っておかないと狂いを生ずる可能性があるので言い残しておく。
以上の6点に概ね集約されるかと思います。
さて、現在の創価学会は第2次宗創紛争の結果、大石寺宗門と決別し、別個の教義を持つ、全く別の宗教法人となりました。分かれた時期としては諸説あるでしょうが、大石寺より破門された①平成3年11月28日(創価学会側はこの日を「魂の独立記念日」としています)、あるいは創価学会全信徒が正式に信徒除名された②平成9年11月30日のどちらかになるでしょう。
さて問題は、平成以降、創価学会は別教団となった大石寺の「客殿」に行くことがなくなりましたから、そもそも「不開門」を創価学会の会長が開くことができなくなりました。信濃町の創価学会総本部には「大誓堂」がありますが、創価学会は教義的にそれを「客殿」として扱ってもいませんし、また「不開門」も建立していません。
「一閻浮提総与の御本尊」とは大石寺奉安堂の戒壇本尊のことですが、創価学会は2014年11月8日に戒壇本尊を「受持の対象」から外し、創価学会本体に「本尊の認定権」があることを表明しました(『聖教新聞』2014年11月8日付)。
「本尊認定の権利が教団にあるなら」https://watabeshinjun.hatenablog.com/entry/2021/09/02/000000
ということは、大誓堂蔵の大石寺64世水谷日昇書写の「創価学会常住本尊」の板模刻が現時点の創価学会の根本本尊で、広宣流布の時には会長(2025年現在は原田稔氏)がどこにあるかわからない「不開門」を開くことが広宣流布なのでしょうか? その時、会長が通すべき人物は誰なのでしょうか。天皇なのでしょうか。それとも政府高官なのでしょうか。
かつて池田大作が言っていたことは宗門と分かれたのでもはや「別にどうでもよい」ことなのでしょうか? 少なくとも上記、昭和40年7月25日の本部幹部会で池田大作氏は「後々のためにいっておかないと、狂いを生ずるからいうのです」「将来のために、私はいっておきます」と述べています。それなのに上記発言は全く紹介されず、『池田大作全集』にも収録されていません。
過去に言ったことが間違いなら間違いと認めれば良いですし、それが間違いではないというのなら、では何が「広宣流布における「不開門」の意義なのか」を、きちんと後世に伝えておくことが必要なはずです。
私はこのブログで、創価学会や日蓮正宗、顕正会と言った大石寺系教団を批判しています。しかしそれは過去の発言との矛盾を認め、誤りがあればそれを認めて謝罪し、訂正して説明をするなら、何の問題もないと思います。過去を誤魔化すからこそ批判するのであって、誤魔化さずに全てを認めて訂正や撤回等をするなら、私がこのブログで教団を批判する理由は雲散霧消するでしょう。
少なくとも当時の会長である池田大作氏が本部幹部会で述べたことですから、その「広宣流布の意義」「不開門が開く」ことの現代における意義を説明すべきでしょう。それがなされていないことは、やはり不誠実であり、過去を誤魔化すことだと私は考えます。
この時の池田大作氏の講演のタイトルは「会長が“不開門”開く」と言うものです。