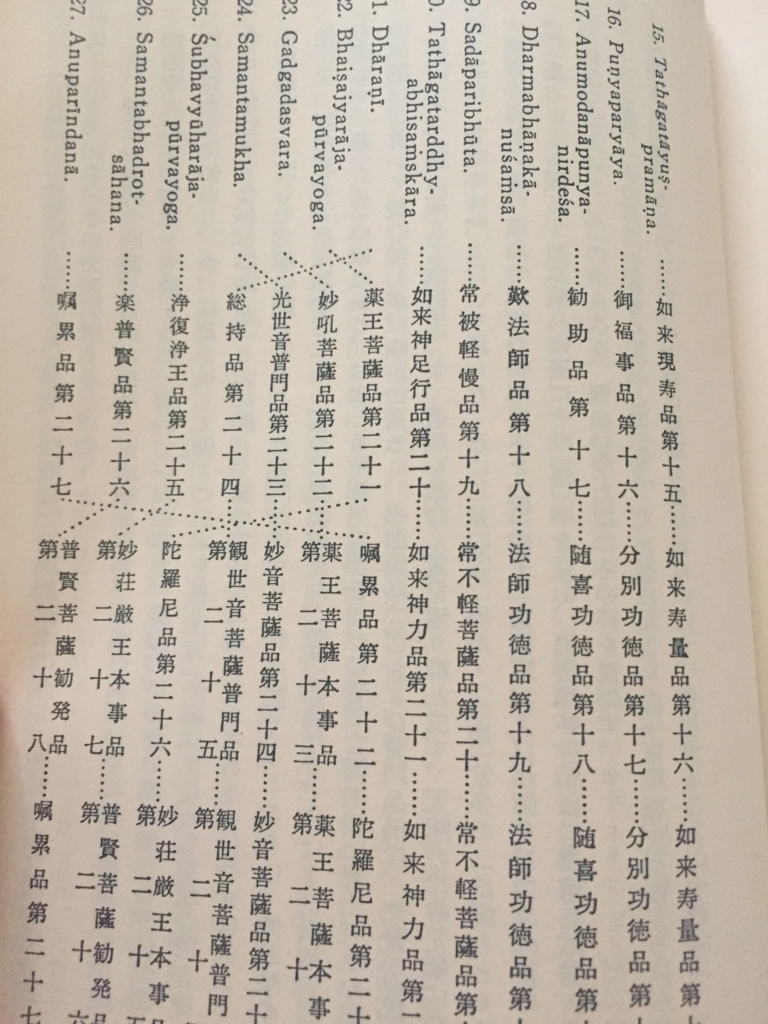いつもみなさん、ありがとうございます。
さて最近様々な方から応援メッセージ等を頂き、本当にうれしいです。いつも感謝しています。
ところで、とある方から牧口思想についての示唆深いメールを頂きましたので、一部を紹介したいと思います。
この方は牧口常三郎の『人生地理学』の国際競争の考え方について「軍事的競争」「政治的競争」「経済的競争」「人道的競争」と競争形式が変わっていくことを示し、次のように指摘されています。
「これから考えると、牧口が軍事的戦争を否定的に考えていたことはいえそうに思えます。
ただし、牧口のいう人道的競争とは、『軍事政治経済的競争を人道の範囲において行う』という消極的なものであって、
創価学会の言うところの平和主義とは異なるものかと思います。
また、競争形式の変更は生命尊重、人道的見地からの変化ではなく、単に経済合理性によるものですので、
ここから、創価学会が主張する
『牧口は人道的競争という言葉を使ったから、平和主義だ』
と牧口思想の人道性を主張するのは無理があるでしょう。
それがまかり通るのは、御書同様、牧口全集も読まない学会員が多いからです。
以上の事から私の私見ですが、
牧口は戦争自体には、経済合理性の側面から言って賛成ではなかった。
ただし、政治のオプションとしての武力行使は否定しておらず、
太平洋戦争については、消極的ながら賛成だったし、戦争するからには勝つべきだと考えていた。
国家主義者だった。
というところかと思います。」
非常に説得力のあるご意見かと私は思います。